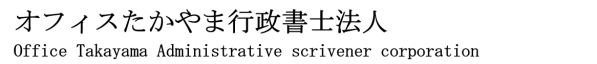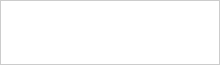目次
育成就労法とは? — 背景と目的
- 「育成就労法(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律)」とは、従来の「技能実習制度」を大幅に見直し、置き換えるかたちで導入される新制度を規定する法律です。
- 目的はこれまでとは転換し、「人材育成」と「人材確保」です。つまり、日本国内で需要のある産業分野において、技能を持った外国人を育てながら、安定的に受け入れようという狙いがあります。
- 従来の技能実習制度では、「国際協力(発展途上国への技能移転)」が強く意識されてきましたが、育成就労制度ではそのような枠組みは弱まり、「国内産業の支え手」を育てることが制度設計の中心です。
いつから始まるのか(施行時期・移行スケジュール)
- この制度を定める法案は 2024年6月14日 に国会で可決・成立し、同年6月21日に公布されました。
- ただし、実際の施行時期は公布日から3年以内、すなわち 最長で2027年6月20日まで に政令で定めるという形になっています。
制度のポイント・特徴
以下が、制度を理解するうえで特に押さえておきたいポイントです。
| 項目 | 内容 |
| 在留資格 | 育成就労分野に属する技能を修得・実践するための在留資格が設置されます。 |
| 育成就労計画の認定 | 受入企業(所属機関)は「育成就労計画」を作成し、所管庁に認定を受ける必要があります。計画には対象業務、技能習得プラン、日本語能力目標、受け入れ体制、費用負担などが含まれます。 |
| 期間 | 育成就労の期間は 3年以内 と定められる見込みです。 |
| 技能・日本語能力の要件 | 技能面では、技能検定3級相当や特定技能1号評価試験合格が求められる可能性があります。日本語能力については、A2相当(または N4)以上を目標とする案が示されています。 |
| 待遇・公平性 | 外国人労働者に対しては、日本人と同等かそれ以上の賃金を支払う義務、寮費・食費などの自己負担の明示、契約内容の説明義務などが強調されます。 |
| 支援体制の整備 | 企業には、育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員などの体制整備が求められる予定です。 |
| 転籍制度 | 一定の条件下で本人の希望による「転籍」が可能になる制度も導入されます。つまり、受け入れ企業から別の事業者に移る道が開かれる可能性があります。 |
| 不法就労助長罪の改正強化 | 外国人を不法に就労させるなど助長行為に対する罰則が強化され、罰金・懲役ともに引き上げられます。 |
技能実習制度との違い(比較)
| 観点 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
| 主目的 | 技能移転・国際協力 | 国内の人材育成・人材確保 |
| 労働力としての位置づけ | 「労働力需給調整としての利用禁止」の原則あり | 労働力確保の手段として位置づけられる可能性あり(制度目的に含まれる) |
| 転籍 | 原則認められない | 一定条件下で本人希望による転籍が可能 |
| 要件・期間 | 実習期間の制限、監理団体の関与などが必須 | 育成就労計画の認定、期間3年以内などの制約あり |
| 保護・支援 | 実習実施前の事前講習、定期監査、実習評価など | より制度設計段階で支援・保護措置が強化される見込み |
受け入れる企業・組織が注意すべき点
- 計画的な制度準備:育成就労計画の作成、社内制度整備、支援体制の確立などが不可欠。
- コスト明示・説明責任:寮費・食費などの負担内容を明確にし、契約時に説明する義務が強調される見込み。
- 労働条件の適正化:賃金や待遇は公平・適正に設定することが求められる。
- 転籍対応準備:転籍制度対応の社内ルールや、費用分担の考え方なども検討が必要。
- 法令遵守・罰則リスク:不法就労助長等に対する罰則が厳しくなるため、受け入れ・管理にあたっては法令遵守体制を強める必要がある。
- 移行期の対応:技能実習制度からの切り替え期で混乱が予想されるため、情報収集と柔軟な対応が重要。
❌ 育成就労所属機関にならないで受け入れることはできません。
■ なぜ登録・認定が必要なのか
この制度では、外国人労働者を「保護しながら育成する」ことが目的であり、
受け入れ企業には 教育責任・生活支援責任・法令遵守責任 が課されます。
そのため、行政が事前に次のような観点で審査を行います:
| 審査項目 | 内容 |
| 法令遵守状況 | 労基法、入管法、社会保険などに違反歴がないか |
| 経営体制 | 雇用・教育・生活支援を継続して行える財務基盤 |
| 支援体制 | 指導員・生活支援担当者・通訳体制の整備 |
| 教育計画 | 技能・日本語教育を含む「育成就労計画」の具体性 |
| 再発防止措置 | 過去に問題があった場合の改善策の有無 |
この審査を通らない企業は、育成就労者を雇用することができません。
■ 登録を受けずに外国人を受け入れた場合
登録を受けずに受け入れた場合は、次のような法的リスクがあります:
- 不法就労助長罪(入管法第73条の2) に問われる可能性
- 罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(改正で罰則強化予定)
- 行政指導・改善命令・認定取消
- 今後の制度利用や補助金申請などにも影響
したがって、未登録のまま受け入れることは法律上不可能です。
■ 登録を行わないで関わる方法(例外的な関与方法)
ただし、「育成就労所属機関」として登録しなくても、
間接的に制度に関わる方法はあります。
| 関与形態 | 内容 | 登録の要否 |
| 委託先・協力会社 | 登録済み企業(所属機関)の下請として、部分的に作業を請け負う | ❌ 直接受け入れ不可(雇用関係がないため) |
| 登録支援機関 | 外国人の生活支援・相談支援を請け負う外部機関 | ✅ 登録支援機関として別途登録が必要 |
| グループ会社間の出向 | 同一グループ内で業務協力する場合は、一定の条件下で認められる可能性 | ⚠ 条件付き・事前確認要 |